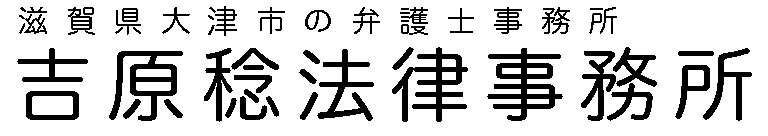目次
1.今はまだ戦後?
2.弁護士・弁護士会は戦争にどう向き合うべきか
3 戦前戦中の弁護士会はどう戦争に向き合ったか
(1)国家総動員法
(2)治安維持法
4.過去の反省を踏まえて今なすべきこと
1 今はまだ戦後?
みなさんよくご承知のとおり、アメリカは、もうかれこれ15年間にわたってアフガニスタン戦争を戦っています。アメリカに開戦を決意させたのは9・11同時多発テロです。しかし、現在の国際法では、戦争は原則として違法とされているので(国連憲章2条4項)、国家が戦争を行うためには何らかの正当化根拠が必要となります。その根拠として、第二次世界大戦後、数々の戦争において多用されてきたのが国連憲章51条に規定される「集団的自衛権」です。アメリカもアフガニスタン戦争の正当化根拠として「集団的自衛権」を主張しています。アフガニスタン戦争にはアメリカ以外のたくさんの国家が参戦していますが、それらの国々の多くも「集団的自衛権」を根拠にしています。アメリカは、日本に対して、「集団的自衛権」の行使容認を求め続けてきましたが、その意図は、アフガニスタン戦争のようなアメリカが行っている戦争に、他の国々と同じように、日本にも「集団的自衛権」を根拠にして参加してほしいという点にあると考えられます。
そして今や実際に、日本は、平成26年7月1日、「集団的自衛権」を行使するための憲法解釈の変更を行い、平成27年9月19日、自衛隊法76条を改正するなど「集団的自衛権」を行使するために必要な国内法の整備を終えました(新安保法制)。このように考えてくると、日本が他の国々と同じようにアメリカの行っている戦争に参加する日も遠くないように思われます。アメリカと軍事同盟を締結しており、憲法解釈という障壁もなくなり、出動根拠となる条文も整備された以上、アメリカからそれを求められた場合に、これを拒絶する理由は最早ないだろうと思います。
もしそのような事態が現実化したとき、そのとき、日本の「戦後」は終焉します。新しい「戦時中」に突入するわけです。そう考えると、今はもしかしたら、もはや「戦後」ではなく、「戦前」なのかもしれません。隣国の脅威にいかに立ち向かうかといった議論に引っ張られるうちに、いつの間にかいつか来た道を辿っているのではないかという不安を感じずにいられません。
2 弁護士・弁護士会は戦争にどう向き合うべきか
そのいつか来た道というのは、言うまでもなく、太平洋戦争に日本が突入していった反省するべき過去のことを指しています。そして、日本が二度といつか来た道を辿らないように、現在、日本弁護士連合会をはじめとして全国の弁護士会が、街頭宣伝など様々な活動を展開しており、それは弁護士会として当然のことです。なぜならば、弁護士の使命は基本的人権の尊重にあり(弁護士法1条)、戦争は最大の人権侵害だからです。
戦争における人権侵害の最たるものは、罪もない一般市民が理不尽に命を奪われることですが、アフガニスタン戦争では、今日までに、アフガニスタン治安部隊やNATO軍・アメリカ軍の行動によって、少なくとも4873人もの民間人が命を落としています。私たち弁護士が尊重するべき基本的人権は何も日本人のそれだけではないことに思いを致せば、アメリカ軍などがアフガニスタン戦争で行っている、こうした人権侵害行為を、弁護士会は黙って見過ごすべきではありません。そして、今般の安全保障法制改正が、アメリカの行う戦争に参加することを可能にするものである以上、すなわち基本的人権の侵害行為に何らかの関与をすることになる可能性を秘めるものである以上、これに対して弁護士会が敏感に反応して反対の声を上げることは、これまた当然のことです。そうしたアンテナを持ちうることこそが、弁護士会の社会的意義であると考えるからです。
3 戦前戦中の弁護士会はどう戦争に向き合ったか
ところで、戦前戦中の弁護士会は一体どのような活動をしていたのでしょうか。現在の弁護士会と同じように、日本が戦争に突入することがないように熱心な活動を行っていたのでしょうか。太平洋戦争を遂行する上では、治安維持法、国家総動員法という2つの法律がとても重要な役割を果たしました。そこで、これら2つの法律の成立について、当時の弁護士会がどのように向き合ったのかを調べてみました。
(1) 国家総動員法
この法律は、労働、物流、公正取引、金融、物価など国民生活、企業活動を広範に統制するものでありながら、統制の具体的内容は法律には定められておらず、国民徴用令などの勅令に委ねられていました。公布されたのは昭和13年4月1日であり、約1か月後の同年5月5日にスピード施行されました。
現在自民党が公にしている憲法改正草案に書かれている緊急事態条項は、この国家総動員法を彷彿とさせるものであることから、日本弁護士連合会や各地の弁護士会は、こぞって反対の姿勢を明確にし、その危険性を国民に訴える活動に取り組んでいます。
それでは、昭和13年当時の弁護士会は、国家総動員法の成立・施行に対してどのような反対運動を繰り広げたのでしょうか。
この点について、いろいろと文献を調べたところ、京都弁護士会史(明治大正昭和戦前編)に、「日本弁護士協会は、この法案に対して憲法違反であることをかかげて反対決議をしたが、東京弁護士会をはじめ各弁護士会は何の意見表明もせず、当会もその例に漏れなかった。」との記述がありました。
ここに出てくる「日本弁護士協会」というのは、「在野法曹が法律問題に関する気焔を呑吐すべき唯一の機関」として、明治29年に全国の弁護士有志が設立した任意団体です。設立時における会員数は全弁護士の半数ほどでした。当時の弁護士会は、検事正の監督下におかれ、議題はあらかじめ検事正に届け出なければならず、会場には検事正を臨席させるか事後に結果報告をしなければいけないことになっていました。そうした場では、在野法曹の立場から司法を批判することが難しかったため、こうした有志団体の設立が求められたのでしょう。
少し話が脱線してしまいましたが、開戦3年前に総力戦(前線と銃後の区別が不明確な状態)に向けて法整備がなされるに際して、当時の弁護士会は何らの意見表明もしなかったようです。
(2) 治安維持法
この法律は、「国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し又は情を知りて之に加入したる者」に懲役刑を科し、その未遂、協議、煽動も同様に処罰することを内容とするものであり、次第に拡大解釈されて、社会民主主義政党や宗教団体にまでも適用されていくことになりました。生類憐の令と並び日本法制史上希代の悪法であるとされます。
この治安維持法成立に対して、当時の東京大学教授末弘厳太郎氏は、東京日々新聞に「過激社会運動取締法案批判」を連載し、かなり強く反対の論陣を張ったようです。また、弁護士有志の任意団体である日本弁護士協会も、法案が「憲法が保障する言論自由の精神に背反し、文化の増強を阻害する」という反対決議を満場一致で採択したようです。しかし、各地の弁護士会による具体的活動については記録が見当たらず、恐らくは成り行きを静観するような感じだったのではないかと思われます。
昭和3年、驚くべきことに、弁護士出身の司法大臣原嘉道が、治安維持法の法定刑に死刑を追加する法改正を緊急勅令によって行いました。このときの、弁護士会サイドの対応について、日本弁護士連合会の「弁護士百年」は次のように記述しています。
「さすがにこのときは原の出身弁護士会も原をよくいわなかったとのことであるが、これに対する各地弁護士会の公的な反対声明のようなものは見当たらない。」
弁護士会も当時の時局に流され、罪刑法定主義の破壊に対してすら、これを座視する態度を取ったようです。枢密院、貴族院の一部、衆議院の野党に反対の動きがあったことを考えれば、残念でなりません。
4 過去の反省を踏まえて今なすべきこと
以上に見てきたように、治安維持法、国家総動員法という、太平洋戦争を代表する2つの悪法の成立阻止という観点からは、当時の弁護士会は、残念ながら、十分な役割を果たしたとはとても言えませんでした。それどころか、開戦後は、積極的に翼賛的関与を進め、陸海軍に対して飛行機を献納したり、「法曹報国の誠を奏す」ため全国の弁護士を組織して「大日本弁護士報国会」を結成したりしました。
このような、開戦に向かう策動に対してほとんど無力であり、そればかりか開戦後は戦争遂行に積極的に協力した過去の反省に立つならば、憲法9条の理念の実現に力を注ぎ、戦争に至るあらゆる可能性の排除に今度こそ全力を傾けることこそが、現在の弁護士会のなすべきことであるように思われます。
ここで他分野の団体に目を移すと、例えば宗教界においては、過去の戦争加担を懺悔した上で安全保障政策に対して積極的なアピールを発信している真宗大谷派のように、きちんと過去の自分たちの行いを反省して現在の活動の礎としている団体が結構あります。
これに対して、弁護士会では、実はそのような自己批判を明確な形で行ったことがありません。それどころか、最近では、安全保障法制に対する意見表明を慎重にするべきだという主張が会内から出てきています。
戦後70年が経過し、戦前戦中の弁護士会を知らない人たちが弁護士会の重鎮を占めるようになってきました。弁護士会が過去に踏んだ轍を二度と踏むことがないように、今一度、私たち弁護士ひとりひとりが、あの戦争に対して弁護士・弁護士会に何も責任がなかったと言えるのかしっかりと自問し、弁護士会が後世に恥じないために今何をすべきか考えるときであると思います。