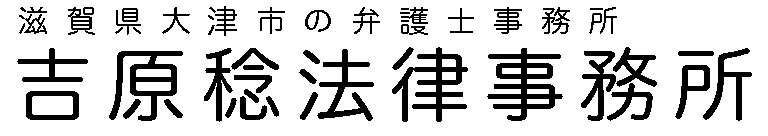目次
1.【解説】
2.【解説】
3.【解説】
4.【解説】
5.【解説】
重大事態調査の開始時期
1.【解説】
2011年10月11日に発生した大津中二いじめ自死事件契機として、2013年6月21日、参議院本会議で「いじめ防止対策推進法」が成立し、同月28日に公布され、同年9月28日に施行された。
同法の28条は、以下のとおり、「重大事態」の調査について規定している。
【いじめ防止対策推進法第28条1項】 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じ
2.【解説】
同条は、従前文部科学省が進めていた「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の在り方について(通知)」などの取組では、教育委員会や学校の隠ぺい等の不適切な対応を防げず、真相の解明や抜本的な再発防止策を講じることが十分に適わず、いじめによる自殺事件等を根絶できなかったことを重大な立法事実としている(1)。
そして、この重要な立法事実を立法府に突きつける大きなきっかけとなったのは、2011年に発生した、大津中二いじめ自死事件であった。当時の大津市教育委員会は、いじめの存在を認めながらも自死との因果関係は判断できなかったとして調査の幕引きを図ろうとし、被害生徒が「自殺の練習」をさせられていたとの情報が寄せられていたことをプレスリリースしていなかったこと等について隠蔽批判を引き起こした(2)。
ところが、いじめ防止対策推進法が施行された後も、残念ながら、各地の教育委員会は、重大事態調査の実施に対して、概して消極的である。例えば、読売新聞社の伝えるところによると、福島市立小学校で2018~2020年、いじめを受けた男子児童が不登校となって適応障害と診断された事例に対して、福島市教育委員会は「重大事態」に該当しないとして、第三者委員会による調査を実施していないとのことである。(3)
福島市教育委員会は、調査を実施しない理由として、①いじめた相手、時期、場所が具体的に立証されていない、②いじめと適応障害との因果関係が不明、の2点を挙げたということであるが(4)、これらを明らかにするのが第三者委員会であると言うべきであろう。
また、筆者が代理人を務める埼玉県川口市を相手どった訴訟(さいたま地裁平成30年(ワ)第1465号)の事案でも、被告川口市は、被害生徒母親の度重なる調査要望に関わらず、一向に「重大事態」として第三者委員会を設置しようとせず、文部科学省から「重大事態として対応しないのであれば、その理由を教えていただきたい」「文科省としては重大事態として扱っていただきたい」とかなり強い要請を受けてもなお、「市教委は重大事態として捉えることはない」と頑なに「重大事態」として第三者委員会を設置することを拒み続けた。
axs教育委員会が文部科学省と対峙する姿勢までとるというのは異常であるが、本当の話である。
(1)小西洋之「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(WAVE出版、2014年、177頁)。
(2)当時の報道を詳細に整理したものとして、北澤毅「『いじめ自殺』の社会学」(世界思想社、2015年、155頁以下)。
(3)2020年9月19日付読売新聞オンライン。
(4)2020年9月19日付読売新聞オンライン。
3.【解説】
なぜ、このような事態が生じるのか。これでは、いじめが隠蔽されてきた、いじめ防止対策推進法施行以前の状況と同じではないかとの思いすら生じる。
その原因は、先に紹介した、いじめ防止対策推進法第28条1項の条文にある。同条では、「重大事態」として調査が開始されるのは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」の2つの場合であるとされている。
そして、ここに「疑いがあると認めるとき」については、解釈上、①学校又は学校設置者が「疑いがあると認め」なければ調査を開始する必要はないという解釈(仮に「主観説」と呼ぶ。)と、②客観的に「疑い」が生じれば調査を開始しなければならない(仮に「客観説」と呼ぶ。)の2つの解釈が可能である。
先に紹介した、福島市教育委員会や川口市教育委員会は「主観説」の立場である。この説は条文の文言をその論拠としている。文理上、「認めるとき」の主語は「学校の設置者又はその設置する学校」であり、そうである以上、その判断は教育委員会や学校に委ねられているとの理屈である(5)。これに対して、文部科学省は、「重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」 が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること。」と述べ、「客観説」の立場であると解される(6)。そして、「疑い」の発生時期については、「被害児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の『いじめ』という言葉を使わない場合を含む。)は、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告 ・調査等に当たること。
児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。」としている(7)。第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会も、「児童等や保護者からいじめられて重大な被害を負ったという申立があったときは、学校の設置者又は学校には『適切かつ真摯に対応すること』が求められ(衆議院附帯決議5項)、その時点で学校がいじめによる所定の被害が生じたという事実関係を把握していなくとも、重大事態が発生したものとして調査・報告等にあたる必要がある。」と述べており(8)「客観説」の立場であると解される。
(5)この解釈をとっていると思われるものとして、坂田仰編「いじめ防止対策推進法全条文と解説」(学事出版、2018年)。同書は、「重大事態」としていじめ防止対策推進法第28条の調査が開始されるためには、「学校の設置者又は学校が、いじめの存在又は被害を認知することを端緒として調査を行った結果、いじめと被害との因果関係について疑いが認められることが要件となる」と説く(96頁)。川口市は、さいたま地裁平成30年(ワ)第1465号事件において、当該頁のコピーを川口市の主張を支える証拠として裁判所に提出している。
(6)「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省、平成29年3月) (7)「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省、平成29年3月)
4.【解説】
それではいずれの説をもって妥当とするべきであろうか。この点については、重大事態調査は現に進行中のいじめ事案の解決を目的として行われるものであるという視点を忘れてはいけないものと思われる。
一般に、いじめの重大事態調査と言うと、いわゆるいじめ自死事案を思い浮かべがちであろうが、身体や財産に重大な被害を生じている事案や相当の期間不登校を余儀なくされている事案も存在する(いじめ防止対策推進法28条1項1号及び2号)。
これらの事案においては、いじめは現に進行中であり、一刻も早くいじめを解消することが重要なテーマとなっている。それゆえ、不登校等の事象がいじめによるものであるとの「疑い」を早期に認定して迅速な対応につなげることが必要不可欠である。この点について、文部科学省は、「重大事態については、いじめが早期に解決しなかったことにより、被害が深刻化した結果であるケースが多い。
したがって、『疑い』が生じてもなお、学校が速やかに対応しなければ、いじめの行為がより一層エスカレートし、被害が更に深刻化する可能性がある。最悪の場合、取り返しのつかない事態に発展することも想定されるため、学校の設置者及び学校は、重大事態への対応の重要性を改めて認識すること。」と述べている(9)。また、いわゆる不登校重大事態(いじめ防止対策推進法28条1項2号)については、不登校の解消も調査の目的とされているのであるから(10)、その調査は出来る限り早く開始されなければならない。
しかしながら、「主観説」によった場合は、先に紹介した福島市教育委員会や川口市教育委員会の事例に見られるように、「疑い」の認定は遅れがちである。
また、「主観説」には、教育委員会ごとに判断がバラバラになってしまい、どの自治体に住んでいるかによって平等に法の適用を受けることができないという原理的な欠点もある。
以上のことから、筆者は、「客観説」をもって妥当と考える。(11)
(8)第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会編「いじめ防止対策推進法」(2015年、現代人文社)
(9)「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省、平成29年3月)
(10)「不登校重大事態に係る調査の指針」(文部科学省初等中等教育局、平成28年3月)は、「不登校重大事態に係る同項の規定による調査(以下単に「調査」という。)の目的は、具体的には、不登校に至った事実関係を整理することで、いじめにより不登校に至った疑いがある児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)が欠席を余儀なくされている状況を解消し、対象児童生徒の学校復帰の支援につなげることと、今後の再発防止に活かすことである。」としている。
(11)なお、「主観説」は、「認める」の主語が「学校の設置者又はその設置する学校」であるという文理を論拠とするが、「認める」の目的語は「疑い」であり、「疑い」は客観的に認定可能であるから、文理の面からも「主観説」だけが唯一の解釈であるとはならない。例えば、本文中で紹介したように、文部科学省は、「被害児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったとき」は「疑い」ありと判断すべきとしており、判断基準は極めて明確である。
5.【解説】
本稿で紹介した問題点については、文部科学省が「客観説」を採っているのに対して、少なからぬ教育委員会や学校が「主観説」を採るという異常と言うべき状況が存在する。
しかし、「主観説」を採っている教育委員会や学校におけるいじめ被害者は、総じて、いじめの実態が明らかにされないまま苦しみの中に置かれている。
いじめ防止対策推進法が制定された経緯や同法の精神からすれば、「客観説」が妥当とされるべきことは明らかと思われるが、文部科学省も全てのケースにおいて、「客観説」での対応を教育委員会や学校に指導しているわけでもない。
しかし、本稿で扱った問題点が現場で少なからぬトラブルを生じていることは、先に紹介した福島市教育委員会や川口市教育委員会の事例に見られるとおりである。
当座の解決策としては、文部科学省から各教育委員会に対して、改めて「客観説」での運用をきちんと通達等の形式で周知徹底することが望まれる。
そしてより根本的には、いじめ防止対策推進法28条1項の「疑いがあると認めるとき」との文言を「疑いが生じたとき」というように改正することによって、解釈問題が発生する余地をなくすべきである。
(文責:弁護士 石川賢治)