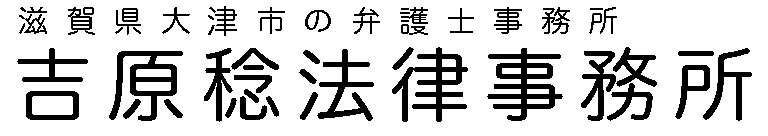目次
第1 事案
原告は、平成27年4月に川口市立中学校に入学し、サッカー部に入部した。サッカー部ではライングループに入ったが、ほどなく、ライン外しのいじめを受けるようになり、練習中にTシャツの後ろの襟首を引っ張られ、首が絞められた状態で倒されたり、ライン上でなりすましによるからかいや誹謗中傷といったいじめも受けた。
原告の母親は、平成27年4月のライン外しのいじめに遭った直後から教員に対していじめ被害を申告し、襟首を引っ張られて倒されたときもサッカー部の顧問に対して申告したが、顧問は事実調査や指導を行わなかった。
原告は、2年生に進学直後の平成28年5月初め頃、サッカー部員と映画に行く約束を破られるいじめに遭い、同月9日から12日まで不登校となった。
登校再開後、原告はサッカー部顧問とノートの交換を行うことになったが、同顧問は、平成28年7月15日頃及び9月5日頃、ノートについて指導する際、原告の頭をこぶしで叩いたり、耳たぶを掴んで引っ張ったりした。その後、原告は、同月14日から2度目の不登校となり、翌15日未明に自傷行為を行った。母親から自傷行為のことを告げられた校長は、サッカーは高いコミュニケーション能力を要するスポーツであり、サッカーの経験の長い子は要領のよい子が多いが、経験の乏しい原告は他の子についていけず遅れてしまっているのではないかという趣旨の発言をした。
平成28年9月27日に開催されたサッカー部臨時保護者会に原告母は学校側から出席しないよう求められたが、その席上、サッカー部顧問は、部員が原告を引き倒したことについて、原告の方でも部員を蹴っており小競り合いである趣旨の発言をした。
平成28年10月12日、原告母は市教委に対して、本件は重大事態に当たるのでないかと述べ、同月24日、県教委は市教委に対して、重大事態であることを念頭に置いて対応しているのかを確認し、同月26日頃には、文部科学省も県教委に対して重大事態としての対応を考えなければならない旨を連絡したが、市教委は、同年12月14日の時点になっても、県教委に対して、重大事態として対応しないと伝えた。
平成29年10月、インターネット上に原告に対するいじめに関するスレッドが作成され、原告や原告母らを中傷する投稿がなされた。原告は、同年11月2日から3度目の不登校となり、同月18日には登校を再開したが、翌12月24日から4度目の不登校となり、平成30年1月30日に自宅を訪れた市教委の指導主事から不登校の原因を尋ねられ、「不安」と答えた。
なお、学校は、平成29年1月、文部科学省や県教委からの再三にわたる指導の末、市教委に対して重大事態発生を報告し、翌2月、調査委員会による調査が開始された。調査委員会は、平成30年3月、ライン外しや襟首を後ろから引っ張られたことなど7件のいじめが不登校の主たる要因である旨の報告書をとりまとめた。
第2 判決要旨
1 体罰について
サッカー部顧問は、平成28年7月15日頃及び同年9月5日頃、原告に対し、指導に伴いその頭を叩いたり耳を引っ張ったりした。同顧問の再現を交えた再現に照らせば、軽く握った拳で原告の頭を打撃音が周囲に聞こえる程度の強さで叩くなどしたと認められるから、少なからぬ程度の有形力を行使したものであって違法なものと認められる。
2 重大事態調査を行わなかったことについて
本件中学校の教諭らは、平成28年9月15日、原告母から、原告が部員らとのトラブルで登校できなくなり、自傷行為に及んだ旨を伝えられ、同月27日頃には、原告母の投稿を知った部員らが誰も原告宅を訪れなくなったことを認識したのであるから、原告がサッカー部内で孤立し、部員らの言動により心身の苦痛を受け、登校できない状態にある恐れを認識し得たと認められる。そして、同年10月24日には、以前の不登校と併せて原告の欠席日数が30日に及んだのであるから、遅くとも同日以降、教諭らは、重大事態の発生を認識し、部員らの原告に対する言動やその背景事情等について調査票を用いるなどした網羅的な調査を行い、その結果に応じた適切な方法で、いじめを防止し不登校を解消するため、部員らへの指導や原告への支援を行うべき義務を負ったと解される。
ところが、教諭らは、個別に部員らから事情を聴き、謝罪を行うことなどに終始していたのであるから、上記義務に違反したものと解される。なお、被告は、原告がカード販売店に誘われなかったことについて、原告母から知らされなかったのだから対応できたはずがないとの主張をするが、自ら事実を調査する義務を負うという点で採用し難い。また、被告は、原告の欠席が原告母の働きかけによるとの判断に基づき、重大事態は発生していないと判断していたと主張するが、重大事態を認知すべきときに重大事態を認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用し難い。
3 いじめの原因が被害者にある旨やいじめがなかった旨の発言について
サッカー部顧問は、部員が原告を引き倒したことについて、サッカー部保護者会において、原告の方でも部員を蹴っており小競り合いである趣旨の発言をし、校長らも、原告母に対し、けんかでありいじめではないと判断していると伝えた。原告が部員を蹴ったということは、原告が自分も攻撃していたのに一方的にいじめられたように訴えているということを意味するから、上記発言をすれば、やがては部員らや原告に学校側の認識として伝わり、部員らが原告に対し不審や反感を強め、また、原告が学校側から嘘つきだと思われていると感じ一層登校に支障を感じることは、容易に予見し得る。サッカー部顧問や校長らは、上記発言をしない義務を負っており、職務上の義務に違反したと認めるのが相当である。
第3 解説
1 重大事態調査を実施しないことが違法とされた初の司法判断
いじめ防止対策推進法28条は、学校の設置者又は学校が、いじめにより児童等の生命、身体、財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、又は、児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき、その事態(重大事態)に対処し、かつ、速やかに事実関係を明確にするための調査を行うべきことを規定している。
しかし、「基本方針やこれらの調査の指針が策定された後も、学校の設置者又は学校において、いじめの重大事態が発生しているにもかかわらず、法、基本方針及び調査の指針に基づく対応を行わないなどの不適切な対応があり、児童生徒に深刻な被害を与えたり、保護者等に対して大きな不信を与えたりした事案が発生」し続けた(文部科学省「いじめ重大事態に関するガイドライン」(平成29年4月)より)。そこで、文部科学省は、平成29年4月に、「いじめ重大事態に関するガイドライン」を作成して、「学校の設置者及び学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者(以下、「被害児童生徒・保護者」という。)のいじめの事実関係を明らかにしたい、何があったのかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たること。」との呼びかけを行ったが、その後も、重大事態調査が適切に行われないケースは後を絶たない。
例えば、平成31年に鹿児島市立中学校で生徒がいじめを受け心療内科に通院し転校した事案について、学校と鹿児島市教育委員会は、重大事態に該当しないとして第三者委員会による調査を実施していなかった。また、同じく平成31年、三重県立高校において不登校となっていた生徒側から「学校でいじめに遭っている」との申告があったにも関わらず学校側は本格的な調査に入らず、その後約1年間、県教委に対する報告もしていなかった。令和3年4月、熊本県宇城市の保護者が、子どもが複数の同級生から「ぶっ殺すぞ」と言われて不登校になったとして市教委に対して重大事態調査を求めたが、市教委は「不登校はいじめが原因ではないため調査しない」との姿勢である。このような例は枚挙にいとまがない。
一方で、文部科学省のいじめ防止対策会議は、令和3年11月22日、重大ないじめが発生しても認知れないことや、調査が迅速に行われないことなどが課題であるとの認識を示している。
本判決は、こうした状況の中、重大事態を認知すべきときに重大事態を認知しない裁量があるとは解されないとして、生徒の欠席日数が30日に達した時点において重大事態として調査等を行わなかったことが職務上の義務違反であり国賠法上違法となると判断した。
さらに細かく言えば、本判決が教職員の職務上の義務と認めたのは、①重大事態の発生を認識し、部員らの原告に対する言動やその背景事情等について調査票を用いるなどした網羅的な調査を行うこと、②調査の結果に応じた適切な方法で、いじめを防止し不登校を解消するため、部員らへの指導や原告への支援を行うことである。
これらの義務の根拠について本判決は明示していないが、①の義務がいじめ防止対策推進法28条を根拠とすることは間違いないところであると思われる。また、②の義務についても、加害者への「指導」、被害者への「支援」との文言から、いじめ防止対策推進法23条2項を根拠とするものと解して差し支えないものと思われる。
いじめ事案において設置者の責任を問う訴訟においては、設置者側から、いじめ防止対策推進法は具体的な義務の根拠とはならないとの法律論が展開されることがあり、これと同旨を述べる裁判例も存在する(佐賀地裁令和元年12月20日判決)。
しかし、従前、学校教育法その他の教育法令が責任の淵源であることは裁判例の共通理解であったと言ってよく、いじめ防止対策推進法についても、学校の責任を導き出し、具体化する役目を果たすものと理解されることこそあれ(采女博文「学校のいじめをめぐる安全配慮義務」(鹿児島大学法学論集49巻2号、平成27年3月、180頁)同旨)、佐賀地裁判決のような理解は、従来の裁判例の理解を完全に逸脱した特異な理解であると言うほかない。
実際、東京高裁令和3年6月3日判決は、いじめ防止対策推進法23条を参照しつつ、担任らは、ある程度の裁量の余地があるとしても、加害児童に対して「さらに強く指導する」、加害児童の保護者に対して「家庭での指導を促す」、加害児童と被害児童とが「接触しないようにする」、被害児童の訴えを真摯に聴いて「精神的に支える」、他の児童に対して「(被害児童を)支援するように仕向ける」などの措置をとるべきであったがこれらの義務を怠ったといわざるを得ないと判断した。
本判決も、東京高裁判決と同じく、いじめ防止対策推進法が具体的な義務の根拠となることを認めた裁判例を積み重ねたものと評価することができる。そして、いじめ防止対策推進法28条の重大事態調査を行わないことが国賠法上違法になると判断した初の司法判断として画期的判決であると評価することができる。
2 重大事態の判断は客観的に行われるべき
いじめ防止対策推進法第28条1項は、「重大事態」として調査が開始されるのは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」の2つの場合であるとしている。
そして、ここに「疑いがあると認めるとき」については、解釈上、①学校又は学校設置者が「疑いがあると認め」なければ調査を開始する必要はないという解釈(仮に「主観説」と呼ぶ。)と、②客観的に「疑い」が生じれば調査を開始しなければならない(仮に「客観説」と呼ぶ。)の2つの解釈が可能である。
訴訟において川口市は「主観説」の立場であった。この説は条文の文言をその論拠としている。文理上、「認めるとき」の主語は「学校の設置者又はその設置する学校」であり、そうである以上、その判断は教育委員会や学校に委ねられているとの理屈である。この解釈をとっていると思われるもの解説書として、坂田仰編「いじめ防止対策推進法全条文と解説」(学事出版、平成30年)がある。同書は、「重大事態」としていじめ防止対策推進法第28条の調査が開始されるためには、「学校の設置者又は学校が、いじめの存在又は被害を認知することを端緒として調査を行った結果、いじめと被害との因果関係について疑いが認められることが要件となる」と説く(96頁)。なお、川口市は、訴訟において、当該頁のコピーを川口市の主張を支える証拠として裁判所に提出してきた。
これに対して、文部科学省は、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省、平成29年3月)において、「重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、「疑い」 が生じた段階で調査を開始しなければならないことを認識すること。」としており、「客観説」の立場であると解される。そして、「疑い」の発生時期については、「被害児童生徒や保護者から、『いじめにより重大な被害が生じた』という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の『いじめ』という言葉を使わない場合を含む。)は、その時点で学校が『いじめの結果ではない』あるいは『重大事態とはいえない』と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告 ・調査等に当たること。児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。」としている。第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会も、「児童等や保護者からいじめられて重大な被害を負ったという申立があったときは、学校の設置者又は学校には『適切かつ真摯に対応すること』が求められ(衆議院附帯決議5項)、その時点で学校がいじめによる所定の被害が生じたという事実関係を把握していなくとも、重大事態が発生したものとして調査・報告等にあたる必要がある。」と述べており、「客観説」の立場であると解される。
この点について、本判決は、双方の主張を適示しておらず、判断部分においても格別の解釈論を展開してはいないものの、結論としては、「重大事態を認知すべきときに重大事態を認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用し難い」と述べており、基本的には客観説に親和的な態度をとったものと解される。
3 教職員が調査もせずに「いじめではない」と発言することは違法である
教職員がろくすっぽ調査することもなく、「いじめではない」「学校生活の中ではよくあること」「成長過程で経験するべきことにすぎない」などとあれこれの言辞を弄していじめを認めないケースは、いじめの現場でよく見かけるところである。
しかし、いじめが場合によっては子どもの命を奪うものである以上、ろくに事実関係の調査もせずにいじめの存在を否定することは極めて危険なことである。そこで、文部科学省も、「学校の設置者及び学校は、詳細な調査を行わなければ、事案の全容は分からないと いうことを第一に認識し、軽々に「いじめはなかった」、「学校に責任はない」という 判断をしないこと。状況を把握できていない中で断片的な情報を発信すると、それが 一人歩きしてしまうことに注意すること。また、被害者である児童生徒やその家庭に 問題があったと発言するなど、被害児童生徒・保護者の心情を害することは厳に慎むこと。」と全国の教職員に対して注意を喚起している(「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省、平成29年3月))。
それでもなお、教職員が軽々に「いじめではない」と発言するケースは一向に後を絶たない。昨今全国的な関心を集めている旭川市の女子中学生のケースでも、亡くなった女子中学生の母親によれば、担任にいじめの疑いを相談した際、担任から「いじめではありません。ふざけただけです。仲のいい子なんです」と言われたとのことである。
こうした状況の中、本判決は、「校長らが、いじめがなかった旨の発言をしたことについて、職務上の義務に違反し、国賠法上の違法がある」旨の判断を示した。全国の学校現場での類似発言に対して警鐘を鳴らすものとして、非常に意義のある裁判例が生まれたものと評価することができる。
(文責:弁護士 石川賢治)